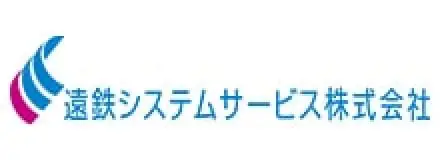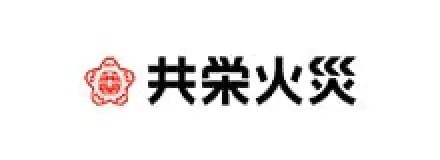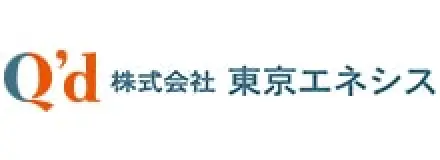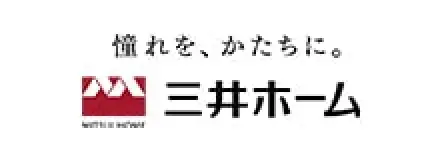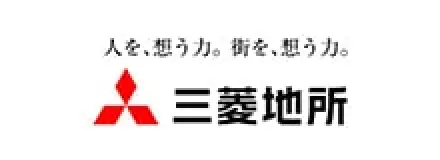出版社がもつ
ビジネストレンドで
未来の人材を育てる
かんき出版の社員研修は、著者を中心とした講師陣と実践的な研修プログラムで、お客様の課題を解決に導きます。
ビジネス書に強い
出版社だから実現できる、
「今」必要な学びの提供
かんき出版の社員研修は、ビジネストレンドを発信し続けている出版社による法人向け研修サービスです。出版コンテンツと著者ネットワークを活かした講演・研修は、「ここでしか聞けない」ものばかり。じっくりとヒアリングをしたうえで、未来に向かって、「今」必要とされるプログラムをお届けします。

Why Choose Us
選ばれる理由
ビジネストレンドの最前線に立つ出版社として、お客様が抱える課題に真摯に向き合い、解決へと導きます。
-

- 質の高い講師陣と
研修プログラム - ベストセラー著者をはじめとした、さまざまな分野に精通した講師による効果的な研修プログラムをご提供します。
- 質の高い講師陣と
-

- カスタマイズ性
- お客様のビジョンや事業戦略、課題に合わせて、プログラムのカスタマイズが可能です。
-
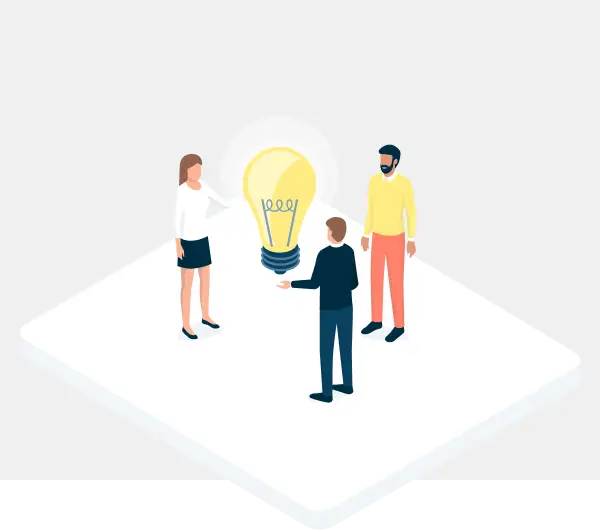
- 丁寧なヒアリングと
課題の見極め - オリジナルのフレームワークに沿ってヒアリングを実施し、コンサルタントがお客様の課題を発見・解決します。
- 丁寧なヒアリングと
Search for Training Services
研修サービスを探す
Training by Assignment
課題から研修プログラムを探す
よくあるお悩み・課題から、最適な研修プログラムをお探しいただけます。
当社サービスや人材育成に関するお悩みについて、お気軽にお問い合わせください。
Case Study
導入事例を見る
かんき出版の社員研修は、IT、製造、金融など、幅広い業界のお客様に導入いただいております。
Achievements
ご利用実績企業様
年間850件
(2022年度実績)の研修実施がございます
当社サービスや人材育成に関するお悩みについて、お気軽にお問い合わせください。